安部公房の代表作のひとつ「砂の女」
この話は不自由の連続とも思える労働生活は幸せなのかという、日常の中で忘れてしまいそうな疑問を投げかけてくれる小説です。
私自身は学生時代に「砂の女」を読んだのですが、社会人になり、実際に自分で労働をし、生活をするという選択をしてから読む「砂の女」はより一層面白く感じました。
「砂の女」のざっくりあらすじ(※ネタバレあり)
<あらすじ>
主人公の男は昆虫採集のため海辺の砂丘地帯を訪れる。最終のバスを逃し、村人に泊まれる場所を尋ねると、砂に埋もれた一軒家を紹介される。
そこは砂の中にぽつんとあり、縄梯子で降りて入る構造だ。家には未亡人の女が住み、日々砂をかき出す作業をしていた。
翌日、男は帰ろうとするが梯子が外され、砂に囲まれたその家から出られなくなる。村人は砂かきの労働力として男を閉じ込めたのだ。
脱出を試みるも失敗が続き、やがて男は女との共同生活に慣れ、砂の中での暮らしに意味を見出し始める。最終的に逃げ出す機会が訪れるが、男はそれを選ばず、砂の中での生活に残ることにしたのだった。
主人公の男は閉じ込められた砂の中の集落で労働をさせられるにも関わらず、最終的に逃げ出さなくなってしまうという話です。
主人公はなぜ逃げ出さなかったのか
砂に埋もれた集落での暮らしは、過酷で劣悪です。
ご飯を食べようとしても砂が上から降ってくるので、傘を差して食べなければいけなかったり、集落が砂に埋もれないよう、常に砂かきをする必要があります。
主人公は教師をしており、妻もいて、砂の集落の外には日常があります。
それでも逃げ出さなかった理由は、「希望を見つけてしまったから」です。
主人公はある日、《希望》と名付けていたカラスを捕まえるための桶の底に水が溜まっていることに気が付きます。
そして、それを見つけて砂の毛管現象ではないかと考え、これを研究することで貯水装置ができるのではないかと気づきます。
砂の集落では水の存在は特に貴重なため、これを誰にも言わずに研究しようと決めます。
砂の変化は、同時に彼の変化でもあった。彼は、砂の中から、水といっしょに、もう一人の自分をひろい出してきたのかもしれなかった。(安部公房「砂の女」新潮文庫)
そして、毎日の日課に溜水装置の研究が加わり、彼は夢中になります。
ある日、一緒に住む女が妊娠し病院に入院することになるのですが、縄梯子がそのままになっていて、逃げ出せることに気が付きます。その時、彼はこんなことを思うのです。
それに、考えてみれば、彼の心は、溜水装置のことを誰かに話したいという欲望で、はちきれそうになっていた。話すとなれば、ここの部落のもの以上の聞き手は、まずありえまい。(安部公房「砂の女」新潮文庫)
そして「逃げるてだては、またその翌日にでも考えればいいことである。」という一文でこの話は終わります。
「誰かにこの発明を見てもらいたい」という気持ちが勝ち、砂の穴の集落という劣悪な環境の中に留まる選択をしてしまうのです。
一見理解し難いですが、ブラック企業と呼ばれるような環境でも、ちょっとした楽しみややりがいを見つけたりする瞬間があり、その一瞬のせいで退職や転職ができなくなってしまう人に似てるなと思いました。
99%が地獄でも、1%の希望があると、人はついそのために頑張ってしまったりしますし、そんな風に社員に一筋の光をちらつかせる企業も少なくありません。
その中でも特に、主人公が感じたような「誰かに認めてもらいたい」という欲望は強烈だと感じます。
男の選択はバッドエンドなのか
側から見たら、砂の中の集落から逃げ出さず留まる選択はバッドエンドのように見えます。
主人公はある意味洗脳されているようにも見えます。
でも、これは私たちの労働生活はこうやって回っている、とも思います。
理不尽に耐え続けているといつしかそれが当たり前になり、やがてそこから逃げるのではなく、そこからどう幸せを見つけ出すか、という風に思考が徐々に変わっていきます。
側から見たらバッドエンド、でも本人にとってはある種のハッピーエンド、という二重構造です。
はじめは村人たちに唆されて村に閉じ込められ、逃げ出すことだけを考えていた男が、はじめは監視役だと思っていた女を一人の人間として意識するようになり、やらされ仕事だった砂に関する作業にもやりがいが生まれてきます。
また、男は教師という肩書きを持っていましたが、それさえも捨てて自分の中の内発的な動機で砂の中に留まることを選んだのは、能動的な選択と言えるのかもしれません。
正しい、正しくないではなく、この小説を読んで自分の労働人生に置き換えて、どう選択するのかを考え続けていくこと。
目の前にぶら下がっている縄梯子を使って今日逃げ出すのか、それともまた翌日以降にするのか。自分自身の環境について考えるきっかけになる話だと感じました。


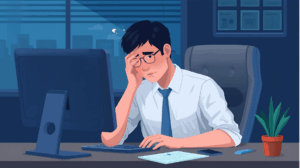




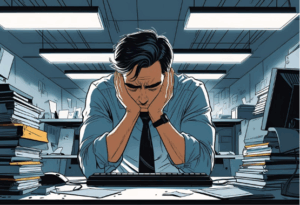


コメント